徳川義直は、家康の九男で尾張の藩祖である。よく部下の意見を聞いた人物だ。いつも「なんでも言え」と言っていた。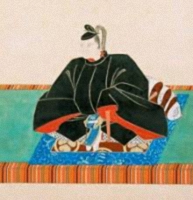
義直は自分の性格を知っていた。彼は「私はすぐに立腹してしまうという欠点がある。だから、腹を立てているときは、絶対に人に会わない」と宣言し、またそれを実行していた。
部下を叱った時も「私の叱り方は正しかったのだろうか? 部下は本当に理解してくれただろうか? 真意を汲み取らずに傷ついただけだったろうか? あるいは私を恨んでいるだろうか?」と、自分自身のこともよく反省した。
そういう義直だから、他人の気持ちを考えず「地球は自分の為に回っている」と思っているような人間が大嫌いだった。特に城の中で「私は生き字引だ」などと尊大な態度をとっている部下は大嫌いだった。
城内に渋谷弥太夫(しぶたに やたゆう)という生き字引がいた。奥番(秘書仕事)が得意で、義直の秘書をしていた。しかし、渋谷の評判はよくなかった。自分なりの「秘書知識とその技法」を持っていて、他の者に教えないのだ。また、自分への「根回し」がないと意地悪をする。
こういう類いの仕事には、極意のようなものがある。しかし、渋谷は気に入った人間には教えるが、嫌いな人間には教えない。トップを囲む人間の流れや人間関係の知識などは、秘書に欠かせないものだ。
だから、こういう職場では、どうしても「長いものには巻かれろ」的な気風が流れ、そういう「生き字引」は「余人をもって代え難い」として、定期異動でも例外にされてしまう。特に、トップの秘密に関することや裏金作りに従事させたら、もうそれだけで、こういう人物の扱いは難しくなってしまう。
この渋谷という男は正にそうだったが、義直は彼を異動させた。それも突然のことで、しかも「現場の係長」へと異動させたのである。人事部は驚愕したが、義直の命令には逆らえない。義直はそれほど強引に渋谷を異動させたのだ。
渋谷は転出させられた。周囲や家族は「いったい、どんな失態をしでかしたのだ?」と騒然とした。ところが、渋谷は黙々と現場で仕事をしたのだ。かつての虎の威を借る狐のような態度はなくなり、人が変わったように勤めた。
渋谷の女房は悪妻で、異動直後「なんの落ち度もないのに」と、義直に恨みがましい気持ちを抱いた。近づいていた連中の足も遠ざかった。盆暮れの届け物も減った。やがて、渋谷の存在を皆が忘れてしまった。結局、渋谷は「義直様に厄介払いされたのだ」ということで片付けられた。
そして2年の歳月が過ぎ去った頃、義直は「渋谷を文書課長にせよ」と命じた。人事部は再び驚愕した。そして「文書課長は藩の最高機密を扱う部署なので、現場の係長からの大抜擢はできない」と反対したのだ。しかし、義直はやはり譲らない。「いいから、やれ」と強引に命じた。
渋谷は文書課長に栄転した。
辞令を渡した後で、義直は「少し話していけ」とくつろがせた。そして「現場へ出した時、私を恨まなかったか?」と聞いた。
渋谷は答えた。「恨みました。一時はトップシークレットをリークしようとも考えました」と、驚くほど正直だ。
義直はなおも渋谷に問いかける。「なぜ、洩らさなかった? なぜ憎い私に報復しなかった?」
渋谷は淡々と答える。「現場には大勢の生き字引がいたからです。現場は技術屋優先です。その生き字引たるや、事務職の比ではありません。理不尽なしきたりで、若い者が泣いています。あれを見て、私もそれまでの自分の姿に初めて気がつきました。私も、ずっと周りを泣かせてきたのだ、と」
そう言って渋谷は顔を上げて義直を見た。「ですから、本当を言えば、今度の異動は私にとってそれほど嬉しくはありません。私は今、現場から生き字引を叩き出す闘争をしていましたから。もう少しで成功するところだったのです」
義直は満面の笑みをたたえた。「わかっている。それは私に任せろ。お前が根性ある男で良かった。これからは本当の力を発揮しろ」と言った。
渋谷は「はい」と力強く頷いたのだった。
どこにでも「生き字引」というのがいる。その仕事に精通していて、知識・技術ともに他人の追随を許さない。従って、人事異動の際にも対象から外される。「余人をもって代え難い」というのがその理由である。
しかし、これは良くないことだ。周りの為にも良くないし、本人のためにもならない。増長しているように見えても本当は本人だって寂しいはずだ。
その人間が休むと、その仕事は誰もまったくわからないなどというのは、そこの管理職の責任問題である。組織はいかなる事態にも備えて、正しく機能するようにしなければならない。
だから「生き字引」こそ、様々な職場に異動させるべきなのである。そうすることで本人の貴重な経験となり、バランスの取れた仕事人として成長していくのだ。
単に「適材適所」だけでは部下は育たない。管理職の仕事は、部下の将来を考え、成長させることも重要な責務なのである。
