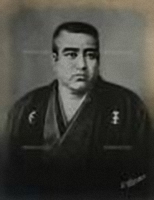西郷隆盛と言えば、維新の志士の一人として有名だが、彼の生涯は波乱に満ちていた。

西郷の若い頃は特に不遇で、トップである島津久光に嫌われて、なんと二回も琉球の島に流されたのだ。最初の島流しの時、彼はふてくされて「俺は鹿児島藩士だ(本社のエリートだぞ)」と言って、それを露骨に態度に表した。
島を「僻地」と言って馬鹿にし、島民を「毛唐(異国人)」と言って馬鹿にした。島民が年に一回くらいしか食べられない白米のご飯を一日三食、タバコもプカプカふかした。本社からの給与の良さを、これ見よがしに誇示したのである。
島の水道は共用の井戸だったが、汲みに行くとき、西郷は遠くから、「こら!どけ!」と怒鳴った。
島民は蜘蛛の子を散らすように逃げた。こんな西郷に、島の人間達が好感を持つはずがない。西郷は初めから自分を「左遷された人間だ」と思い、「左遷地の職場にいる奴は、皆、クズで程度が低い」と思っていた。
西郷と現地人との間の空気は険しく、解け合わなかった。しかし、そういう傲慢な西郷も、月日を重ね、現地を見つめているうちに、いろいろなことがわかってきたのは二回目に、この島に来たときだ。
この頃から西郷の中で何かが変わり始める。
何よりも島民の暮らしぶりを見て、島民のニーズ(需要)に鹿児島本社が全く応えていないということに気がついた。本社の現地認識は根本的に間違っている。だから、島に置かれた支店(出張所)は、的外れでチグハグな仕事をしているのだ。
現地もまた、本社のエリート達のご機嫌を伺うばかり、正しい情報を提出していないのだ。本社の判断・指示を誤らせているのは、島の支店の責任である。
現地採用の社員はともかく、本社から来ている人間は、とにかく一日も早く鹿児島に帰りたい一心で、現地の実態を歪めてまでも、本社の意に沿おうとする。こういう実態を西郷は知った。そして改めて腕を組み、考え込んだ。
「俺は間違っていた」と悟った。現代の言葉で言えば、「支店も本社も、現地に住む人間のニーズに全く応えていない」ということを悟ったのだ。
では、現地に住む人間のニーズに応えるためにはどうすれば良いのか。まず、自分の考え方を根本から変える必要がある。「この島が左遷地」であるという考えを捨てる。すなわち、自分も「左遷された人間」だという考えも捨てる。
「この島も、我が社にとって大切な顧客のいる場所だ」と考える。左遷だの、栄転だのつまらない観念から脱却し、「我が社にとって大切な市場」なのだ、という考えを持つべきなのだ。
そう悟った西郷は、生活態度を一変させた。まず、「支店の仕事を現地のニーズに適合させる」ということに主眼を置いた。それには、ニーズのマーケティングが必要だ。西郷は積極的に島の中を歩き始めた。そして、島民に話しかけ、意見を聞いた。
しかし、今までの西郷の態度を見ていれば島民としてはそう簡単に話に乗れない。上手いことを言って騙す気だろう、と疑うのも当然だ。
西郷は根気強かった。彼は誠心誠意歩き回った。私塾を開いて、子供に学問を教えた。島の娘を妻に娶った。
島民の西郷を見る目が変わってきた。「西郷さんは島に永住する気だ。もう本社志向の腰掛けではない」という評判が立った。島民は少しずつだが、本当のことも言い始めた。
西郷は、この島民の本音を元に下記の二点に注力した。
- 本社への間断の無い意見提出
- 島支店の根本的改革
今までの西郷は、島を左遷地と考え、島民を毛唐と言って馬鹿にしてきた。しかし、発想を変えた彼は、島民を一人一人の人間として見た。そうすると、それぞれの価値観から、それぞれのニーズを持っているのだと解った。
端的に言えば、「人間は、一人ずつ全部違うニーズを持っている」、それをどのようにまとめればよいのか、ということを学んだのだ。この経験が彼を大物政治家に育てていくことになる。
「顧客を離れて企業は成立しない」とは、誰もが言う。しかし、その顧客を観念的にしか捉えていまいか。特に本社のデスクワーク組は、そうではないのか。本社も、現地の顧客とその実態に直接向き合う必要がある。そのためには、現地に行ったら現地の立場に立つことだ。この西郷の姿勢は、誰よりも島民が支持し、支店員の何人かも支持した。
「西郷を本社に戻せ」という声は、むしろ本社から上がった。しかし、西郷は本社に戻っても、長く「大島三右衛門」と名乗って、島の名を姓にしていた。
それほど「左遷された現地」に深い愛情を持っていたのである。そして、この左遷が無かったならば、おそらく後に坂本龍馬と共に、大政奉還を成し遂げた西郷隆盛もあり得なかったことだろう。